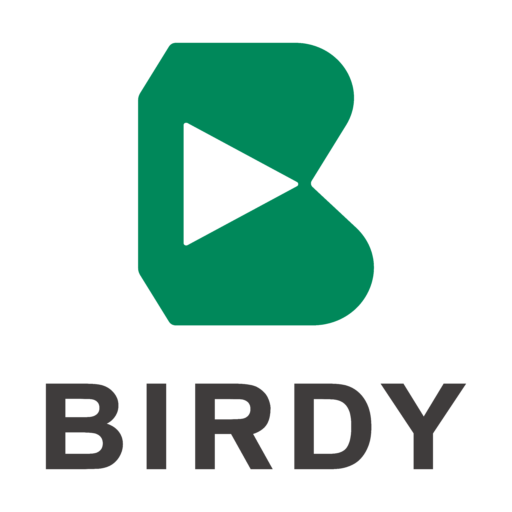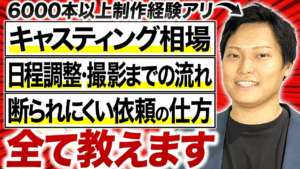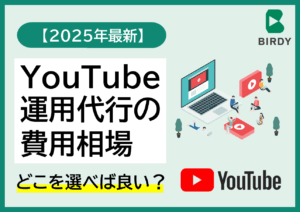「毎週しっかり動画を出しているのに、登録者が全然増えない」
そんな焦りや不安を感じていませんか?
YouTubeは、正しい戦略と手順を踏めば、確実に成果を出せるマーケティングチャネルです。
しかし、何となく運用してしまって伸び悩んでしまうケースも少なくありません。
そこで本記事では、登録者0人〜1万人の各成長フェーズごとに、「やるべきこと」と「やってはいけないこと」を具体的に解説します。
\YouTube運用にお悩みの企業様へ/
BIRDY(バーディ)は、上場企業を含む累計120社・1万本以上の実績を持つ、法人専門のYouTube運用支援会社です。
戦略設計から撮影・編集・内製化まで一気通貫でサポート可能ですので、まずは一度ご相談ください。
登録者0〜100人|アルゴリズムに評価されるための土台づくり

YouTubeチャンネル運用において、最初の壁となるのが、登録者100人の達成です。
初期フェーズは、YouTubeがチャンネルの属性やターゲットを学習する重要な期間。
この段階で狙うべきは、バズではありません。
大切なのは、「誰に見てもらいたいチャンネルなのか」をYouTubeに正確に伝えること。
焦らずに足場を固めることが成果につながります。
ポイント1.30本の動画投稿で、登録者100人を目指す
まずは、30本の動画投稿で、登録者100人達成を目標にしましょう。
達成の目安期間は、早ければ2か月、遅くても3〜4か月が一般的とされています。
ですが、3か月経っても思うように伸びないケースもあるので、焦りは禁物です。
そんなときこそ、外部拡散やテコ入れ施策に頼るのではなく、地道な土台づくりに集中することが、長期的な成果への近道になります。
ポイント2.アルゴリズムに正しいチャンネル属性を伝える
チャンネル立ち上げ初期に、SNS投稿や広告配信などの外部施策(=YouTube外から視聴者を集める施策)を行うと、かえって逆効果になることがあります。
というのも、ターゲット外の視聴者が流入すると、YouTubeに誤ったチャンネル属性を学習されてしまう可能性があるからです。
⚫︎初期訪問者の偏り(魚料理好きが多い)
↓
⚫︎YouTubeが「魚向けチャンネル」と誤学習
↓
⚫︎肉料理動画なのに魚好きユーザーに多く表示される
↓
⚫︎CTR低下・視聴維持率低下
↓
⚫︎露出が減り、本来の肉好きユーザーに届かない
↓
⚫︎チャンネル成長が鈍化
こうしたミスマッチを防ぐためにも、最初の100人までは、ターゲットに合った視聴者に向けた動画を地道に投稿し続けることが重要です。
ポイント3.検索流入を意識したコンテンツ戦略
初期チャンネルにとって最も強力な流入源のひとつが、YouTube検索経由の視聴です。
YouTubeアルゴリズムからの評価がまだ低い段階でも、検索結果に表示されれば、興味を持つ視聴者に動画を見つけてもらいやすくなります。
検索流入を伸ばすポイントは、以下の3つです。
- 複合キーワードで企画を作成する
例:「ノートパソコン 選び方」「ノートパソコン 買い方」など - 検索ボリュームが多いキーワードを選ぶ
ツール例:Googleキーワードプランナー/Ubersuggest(いずれも無料プランあり)
※目安:月間検索数1,000件以上のキーワードを複数選定 - 検索ユーザーの意図に沿った構成・タイトル・サムネイルにする
これらを徹底することで、ターゲット層の視聴者が自然と集まりやすくなり、結果的にアルゴリズムにも正しいチャンネル属性が伝わりやすくなります。
そして、検索流入を成功させるために欠かせないのが、キーワードリストの作成です。
具体的な作り方については、以下の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
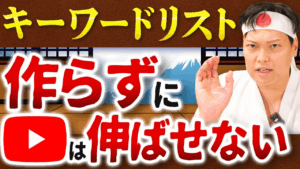
登録者100〜500人|外部拡散の開始
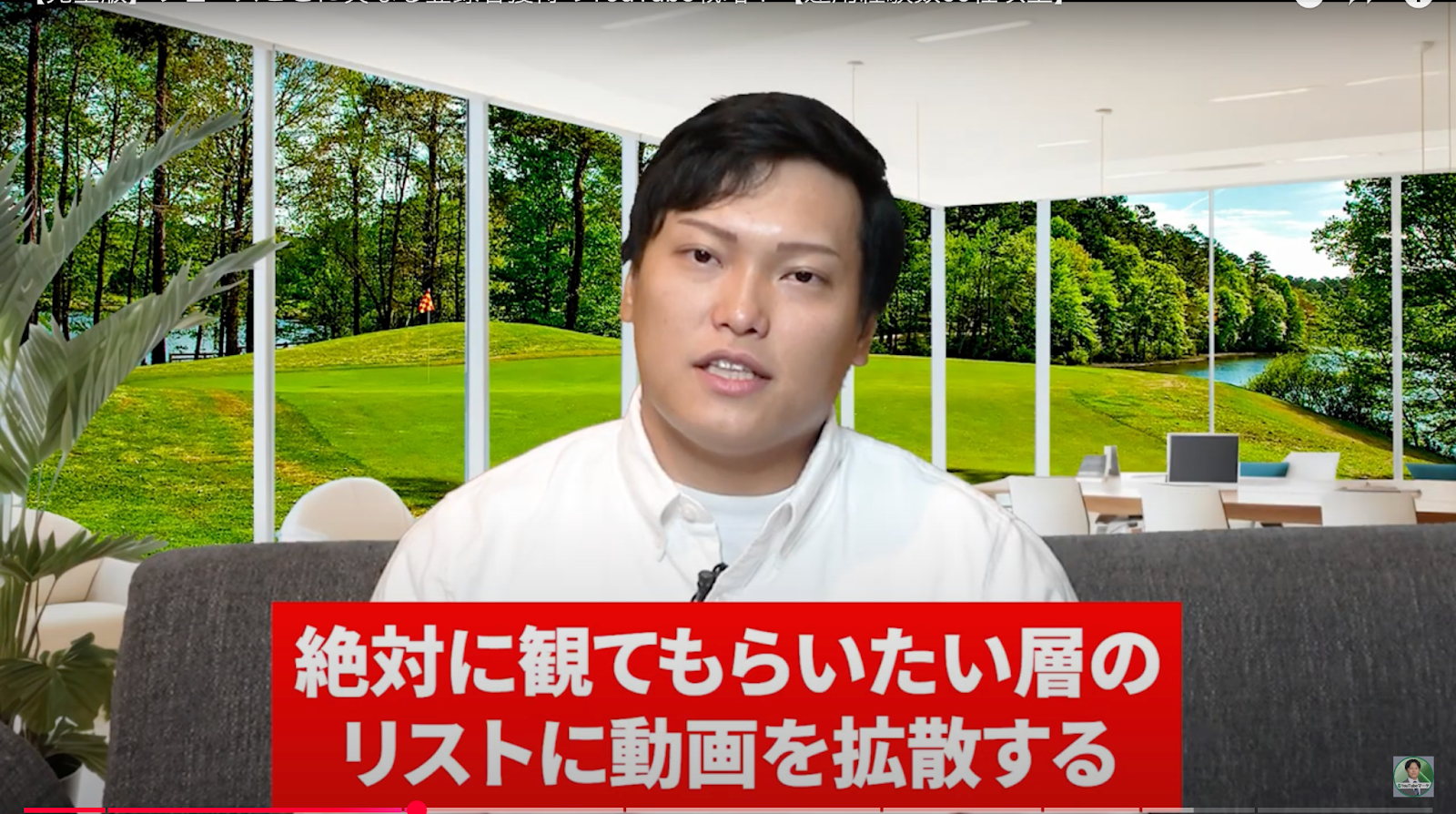
登録者が100人を超えたら、少しずつ外部拡散をスタートします。
ただし、闇雲に拡散するのはNGです。
繰り返しにはなりますが、ターゲット層とズレた視聴者が流入すると、本来届けたい層に届かなくなってしまい、チャンネルの成長にはつながりません。
この段階で効果的なのは、社内の協力体制の構築と、既存の顧客リストを活用したターゲット配信です。
ポイント1.社内での自然拡散を促す
まず取り組みやすいのが、社内関係者への協力依頼です。
とはいえ、ただ再生してもらうだけでは意味がありません。
YouTubeのアルゴリズムは、単なる再生回数よりも視聴の質を重視しています。
そのため、協力を得る際は以下の点を共有しておきましょう。
- 動画は最後まで視聴(途中離脱はNG)
- 倍速視聴は禁止
- 複数動画(目安:3本以上)を視聴してもらう
こうすることで、YouTubeが「興味関心が近いユーザーが集まっているチャンネル」と判断し、おすすめや関連動画への露出が増えやすくなります。
ポイント2.DMリストを活用したターゲット配信
もう一つの有効な方法が、すでに自社で保有している見込み顧客リストへの段階的配信です。
BtoB企業であれば、営業リストやメルマガ読者、セミナー参加者などが該当します。
- 視聴者の属性がチャンネルと一致するリストのみを使う
- 一斉送信ではなく、少数ずつ段階的に送信する
登録者500〜1,000人|作り込み型の企画動画とトレンド活用で加速
登録者が500人を超えると、視聴者の「質」と「量」がある程度安定してきます。
このフェーズでは、コアファンを増やしていくために、チャンネルの信頼性や専門性を明確に打ち出すことが重要です。
ポイント1.作り込み型の企画動画を投入する
このタイミングで特に効果的なのが、「看板動画」として機能する、力の入った企画コンテンツの制作です。
制作に工数はかかりますが、視聴者の満足度や滞在時間の向上につながり、チャンネルの評価向上にもつながります。
- 社員や顧客の1日に密着したドキュメンタリー形式
- 1時間以上の網羅型・完全解説コンテンツ
- ストーリー性や継続性のあるシリーズ動画
こうした動画は、視聴者の信頼が育ちつつあるこのフェーズだからこそ、専門性・深さを武器として発揮しやすくなります。
<動画コンテンツの例>
ポイント2.トレンド動画で検索需要を取り込む
もう一つの強力な打ち手が、時事性のある「トレンド動画」の活用です。
世間で注目されている話題や業界ニュースを、自社ならではの視点で解説することで、検索流入やレコメンド経由の新規視聴者を獲得できます。
- 業界ニュースや法改正に対する専門的な考察
- 社会的トピックと自社の専門領域を掛け合わせた時事解説
トレンド動画は短期的に再生数を伸ばしやすく、検索上位に表示される確率も高いため、新しい視聴者獲得につながります。
登録者1,000人〜|業界インフルエンサーとのコラボへ

登録者が1,000人を超えると、チャンネルの信頼性が高まり、他チャンネルとの連携がしやすくなるフェーズに入ります。
特に、同業界の小〜中規模インフルエンサーとのコラボが現実的になり、視聴者属性が近いユーザーを自然に取り込める点が大きなメリットです。
- 早めの事前準備がカギ:コラボは企画・調整・撮影に時間がかかるため、2〜3か月前の段階から候補選定を始めておくとスムーズ
- 視聴者属性の一致を確認:年齢層や興味関心がずれていると、かえって既存視聴者の離脱やアルゴリズムの混乱につながる
- 異業界とのコラボも視野に入れる:世界観や価値観に親和性がある場合、異業種コラボも有効
登録者1万人〜|他業界とのコラボと多チャネル展開

登録者が1万人を超えると、チャンネルが信頼ある情報メディアとしての立ち位置を持ち始めます。
このフェーズでは、他業界とのコラボや複数チャネルでの発信といった、次のステージに向けた展開が可能になります。
ポイント1.他業界とのコラボで“横の広がり”をつくる
1万人を超えると、一定の認知と専門性が確立されており、異業種のYouTuberや企業とも相互に価値あるコラボが実現しやすくなります。
異なる業界の視聴者にリーチできるため、新規視聴者層の獲得とブランド認知の拡大が期待できます。
ただし、あまりにも視聴者の属性がズレていると、本来のターゲット外の視聴者が一時的に流入し、本当に届けたい視聴者層に動画が表示されにくくなる可能性があります。
そのため、このフェーズでもコラボ相手の選定は慎重に行うことが重要です。
ポイント2.多チャネル展開で接触機会を増やす

YouTube単体ではなく、ほかのチャネルも活用することで、視聴者とのタッチポイントを増やし、より深いエンゲージメントを構築できます。
特に効果的なチャネル・施策は以下のとおりです。
- TikTokやYouTubeショートでの短尺コンテンツ配信
- SNS連動(X、Instagramなど)で動画の背景や意図を補足
ただし、短尺動画やショートコンテンツは再生数が伸びやすい反面、企業チャンネルの場合は長尺動画との温度感にギャップが生じやすい点に注意が必要です。
【重要】たとえ3か月登録者が伸びなくても焦らない!
企業チャンネルでよくあるのが、「思ったように登録者が増えない」と感じた段階で、著名人とのコラボやSNSなどを使った拡散に頼ってしまうパターンです。
一見効果的に思えますが、視聴者属性がズレてしまい、YouTubeのアルゴリズムがチャンネルを正しく評価できなくなります。
登録者が1,000人を超える頃には、アルゴリズムの評価が安定し、そこから加速度的に伸びやすくなります。
たとえ思うように伸びなくても焦らず、メディアとしての価値を丁寧に育てていく意識を持つことが重要です。

まとめ:一貫したチャンネル属性の統一が成功のカギ
どのフェーズにおいても重要なのは、ターゲット層に合わせた企画・動画制作です。
YouTubeのアルゴリズムに正しく認識されるには、「誰に向けて、何を発信している」チャンネルなのかをブレずに伝え続ける必要があります。
特に、コラボや外部拡散などの施策を取り入れるタイミングは、登録者が100人を超えてからにしましょう。
YouTubeの運用代行・コンサルティングはBIRDYにお任せください!
株式会社BIRDY(バーディ)は、東京都新宿区を拠点に活動する企業専門のYouTube運用代行・動画制作・コンサルティング会社です。戦略設計から法人チャンネル立ち上げ、撮影・編集、内製化支援まで一気通貫で対応できる日本でも数少ないパートナーとして、上場企業複数社を含め、累計120社以上のYoutube支援・10,000本以上の動画を企画・制作してきました。
代表の鳥屋自身が実際に運用してきたYouTubeチャンネルの知見を活かし、机上の理論ではなく“実戦ベース”で成果を出せるサポートを提供。ビジネス系チャンネル・法人チャンネルのノウハウは日本トップクラスです。マーケティング×制作の両軸から企業YouTubeを成功へと導きます。
「YouTubeを活用して集客・採用・ブランディングを強化したい」という企業様は、ぜひ一度ご相談ください。